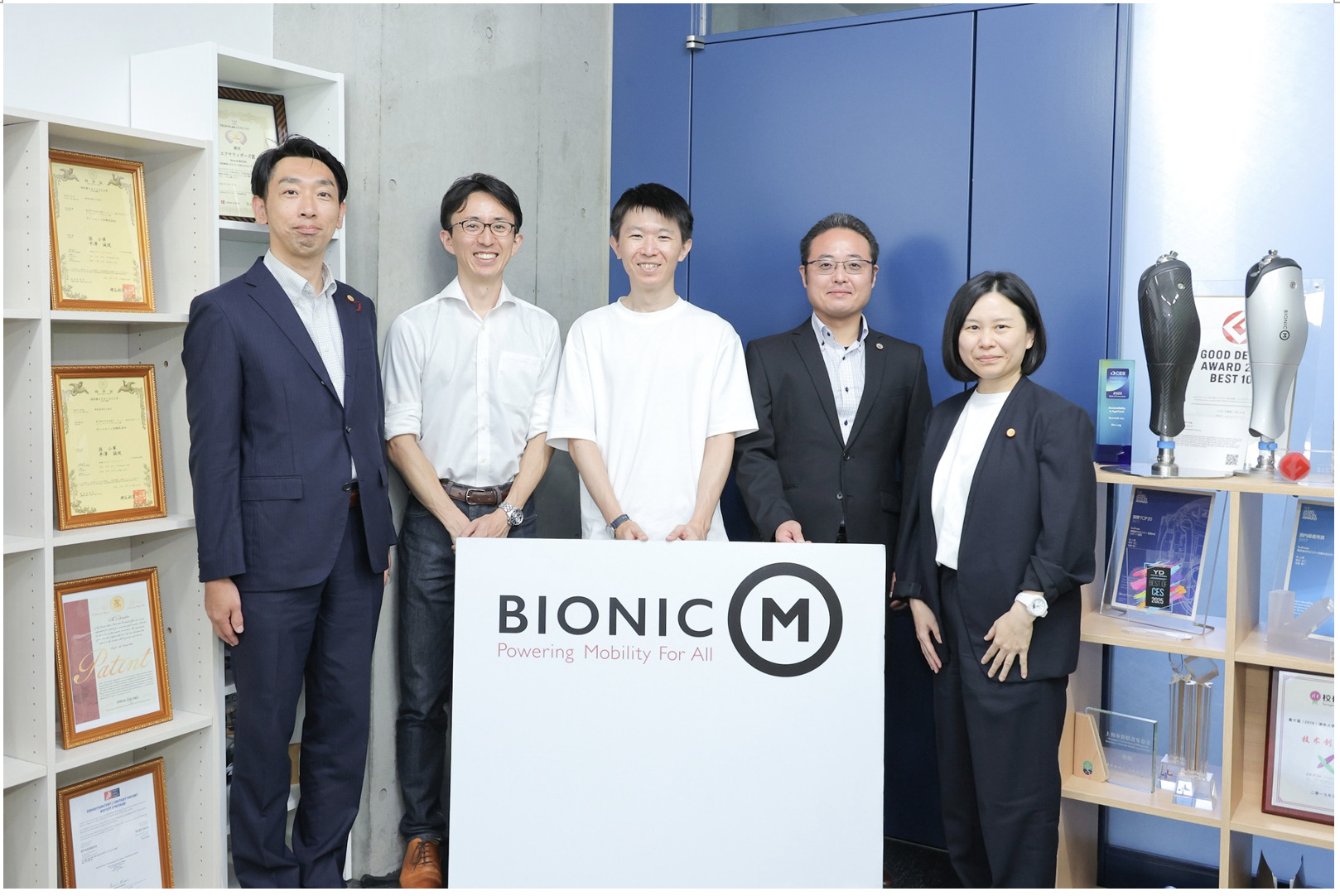事例紹介
BionicM株式会社
技術革新が進む現代においても、モビリティの根幹である「自身の足」に関する課題は、いまだ解消されていません。
筋力の低下や怪我、病気、切断などにより足に不自由を抱える方々は、身体的な制約だけでなく、行動の自由を失うことによる精神的な苦痛も抱えています。
こうした課題に対し、「Powering Mobility for All(すべての人々のモビリティに力を)」をミッションに、義足自体が動力を持ち、動作をアシストする「パワード義足」の開発・提供を通じて、誰もが自身の足で自由に動ける社会の実現を目指しているのが、BionicM株式会社です。
同社は、身体の筋肉の特徴を工学的に模倣・活用した独自の駆動機構や高精度な制御アルゴリズムなど、高度な独自技術を有しており、こうした技術力を背景に、特許の取得や知的財産の活用を軸とした販売戦略にも積極的に取り組んでいます。そんな同社の技術開発と知財戦略の取り組みについて、執行役員CTOで工学博士の金石大佑氏を中心にお話を伺いました。

ロボット技術で自然な歩行をアシスト
BionicMが変える、新時代の義足
ーーまずは、BionicM設立の背景についてお聞かせください。
当社の創業には、代表である孫小軍の実体験が深く関わっています。
孫は9歳で病気により右足を切断し、義足が手に入らないまま中国で15年間、松葉杖による生活を余儀なくされました。両手がふさがる日常の不便さを長く体感してきた中、2011年に交換留学で来日し、日本の福祉制度のもと初めて義足を装着。両手が解放されるその自由さに強い衝撃を受けました。
その後SONYでエンジニアとして勤務する中で、義足ユーザーとして「自分だからこそ、より良い義足をつくれるのではないか」という想いを抱くようになります。そうした想いからSONYを退職し、東京大学のロボティクス研究室(JSK)に進学。ロボット技術を義足に応用する研究に取り組み、その成果をもとに2018年、BionicM株式会社を設立したのが当社設立の大まかな経緯です。

ーーどのようなビジネスを展開されているのですか?
電動で動作をアシストする、”パワード義足”の開発・製造・販売が主な事業です。
主軸製品は、「Bio Leg®️」という義足で、単なる義足ではなく、電動で動作を補助する能動式義足であり、膝関節の動力補助を通じてユーザーの動作をサポートする点に特徴があります。
この義足には、人間の筋肉の特徴を模倣した独自の駆動機構と、動作を適切に補助する高精度な制御アルゴリズムが搭載されています。これにより、ユーザーの直感的な操作に基づいて、義足は滑らかな動作補助を提供し、従来の義足で課題となっていた非切断側の足(義足側の足ではないもう一方の足)への負担なども大幅に軽減することができます。ただ歩くのではなく、よりバランスのとれた「きれいに歩く」を実現する新時代の義足だといえます。
(※®は、登録商標であることを知らせるマークになります。)
ーーまさに独自技術の塊ですね。
当社のコア技術となるのは、人間の筋肉の特徴を工学的に模倣した「バイオニックマッスルテクノロジー(Bionic Muscle Technology)」です。一言でいえば、人の動作を支える人工的な筋肉のような仕組みです。
このシステムには、ユーザーの動きや意図を感知するセンサーが備わっており、モーターの力でその動作をスムーズにアシストします。これにより、従来の動力を搭載しない受動式義足の課題を解消して、「椅子から立ち上がりやすい」「アシストにより身体の負担が小さく感じる」「ゆっくり歩く際も膝がしっかり曲がってくれてつまずきにくい」といったユーザーのニーズに応えた製品となっています。競合のパワード義足と比較しても、「直感的な操作によりわずかな訓練期間で使える」「歩行や立ち座りの一連の動作が自然で、まるで自分の足のように滑らかに連動する」といった使用感を実現しています。
従来型受動式義足の限界
高齢者が直面する肉体的負担の実態
ーー義足の市場性や現状、求められるニーズについて教えてください。
義足を取り巻く現状として、世界には足を切断した人が4,000万人以上いるといわれています。
主な原因は糖尿病や血管障害などの病気で、次いで事故や災害、戦争による外傷が続きます。米国のデータによれば、切断者全体の約9割は45歳以上の中高年で、足腰の衰えから義足を使いこなせず、車椅子生活や寝たきりになる例が多く見られます。
これは本人のQOL(生活の質)を低下させるだけでなく、介護の負担や医療費増加など社会的問題にも直結します。そもそも、高齢で足腰が弱っていると、義足を満足に使いこなすことが難しく、非切断側の足への負担が増加してさらなる機能低下を招くという悪循環も起こります。特に、従来の動力を持たない受動式義足は、義足ユーザーが自らの筋肉で振って使うという特性上、日常動作を十分に補助できず、こうした状況を招きやすい傾向にあります。

ーー動力を持たない従来の受動式義足は、足腰の衰えた人にとっては、かえって大きな肉体的負担を強いることもあるのですね。
おっしゃる通りです。
一方、当社の「Bio Leg®️」は、義足自体が駆動して動作をアシストするパワード義足であり、自然でバランスのとれた美しい歩行を実現します。これにより、足腰への負担を大幅に軽減し、ユーザーの日常生活の幅も大きく広がります。
こうした「Bio Leg®️」ならではの自然な使用感を実現する上では、当社代表である孫自身が試験的に「Bio Leg®️」を日常生活で使ってみて、実際の使用環境での課題や改良点を徹底的に洗い出してきました。買い物や階段の昇降、長時間の歩行といったリアルなシーンでの検証とフィードバックを繰り返すことで、単なる理論上の性能ではなく、「使っていて疲れにくい」「動きが自然」「心理的な負担も減る」といった、ユーザーが本当に求める性能を形にしてきました。
「Bio Leg®️」のような動力アシスト機能を備えた「パワード義足」を扱うメーカーはまだ世界に3社しかありません。その1つが当社で、残りはアイスランドの大手メーカーとオランダの新興メーカーです。
推測ではありますが、競合の大手メーカーは、従来のロボット技術に基づいた設計・開発を行っているのに対し、当社はユーザーファーストの視点から、日常生活に重きを置いた設計・開発を行っている点で差別化を図っています。
コア技術を守りながら攻める知財活用
専門的な分析力と俯瞰視点による成長支援の重要性
ーー貴社は日本とアメリカの2拠点体制で事業を展開していますが、なぜこのような体制を選択されたのでしょうか。その背景や狙いについてお聞かせください。
アメリカは、義足においても世界最大の市場があるからです。
実は設立当初、アメリカではなく日本と中国でテストマーケティング的に事業を展開していました。なぜならば、欧米において義足は医療機器に分類されるのに対して、日本と中国では福祉機器として扱われ、医療機器登録なく販売が可能だからです。そのため、テストマーケティングの観点から非常に開発に取り組みやすく、まずは日本と中国において実際のユーザーに使用していただく形で、製品のブラッシュアップを重ねてきました。
そうした実績と改良を経て、製品の機能面でも一定の受け入れが見込めると判断し、世界最大の市場であるアメリカへの進出を決断しました。もちろんアメリカでは医療機器としての登録が必要となりますので、2023年にFDAの医療機器登録を行い、2024年には、医療保険の適用承認も取得しました。同年から販売も開始し、現在ではユーザーからのフィードバックを反映しながらさらなる製品改良とサービス向上に努めています。これにより、アメリカ市場での存在感を着実に高め、グローバルな事業拡大の基盤を固めていくことを目指しています。

ーーそうした独自性の高い技術を守り、活かすための知的財産戦略についてお聞かせください。
特許庁の知財アクセラレーションプログラム「IPAS」を通じて、知見が豊富で信頼できる弁理士の方をご紹介いただき、その後も一緒に知財戦略を考えてもらっています。
具体的には、制御・機構・デザインといったハードウェア全般に関わる特許などの知財管理や出願戦略に加え、数年先を見据えた競合対策や海外進出を前提とした知財活用戦略の立案まで、幅広い支援を受けています。
また、これまでに国内外で複数の特許を取得して、パワード義足の核心部分を押さえることで、大きな競争優位を築いています。
ただし、そうした重要な部分を必要以上に公開すれば、”抜け道”を突かれるリスクも増大します。したがって、そうした部分のリスク管理や守るべきコア技術の見極め、技術の公開範囲といった点についても、弁理士の方から助言を受けながら慎重に検討を進めています。
ーー弁理士をより効果的に活用するにあたり、意識されていることはありますか?
「自分たちが何をしたいのかを明確にして伝える」ことです。
弁理士の方は文字通りのプロフェッショナルであり、こちらの要望がはっきりしていれば100%のサポートをしてくれます。しかし、「何をしたいのか」が曖昧なままだと有意義なアドバイスを受けられない可能性があると思います。
そこで、弁理士の方に頼るときは、「こういう戦略をとりたいが、どうすればいいか」と具体性をともなった相談を行うことを心がけています。それによって、自分たちのビジネスにとって有効な策を提案してもらえるようになります。
そんなIPASの活用で得た恩恵は、医療機器や生体工学・ロボティクス分野に明るい弁理士の方を紹介してもらえたことです。また、投資家とのコミュニケーションの方法などに関してもアドバイスいただき、知財の取得戦略だけでなく、外部への効果的な情報発信の方法についても学ぶことができました。
ーー弁理士に期待したいことはありますか?
当社は2015年に創業し、2018年に法人化して本格的な事業を開始し、スタートアップとしての試行錯誤を経て、ようやくトンネルを抜け、事業の輪郭が明確に見えてきました。
まだそんな段階なので、知財担当を置く余裕もなく、自分たちで勉強しながら業務を回しているのが実情です。だからこそ、弁理士の方から「こんなこともできます」「特許出願だけじゃなく、他社特許の分析や市場動向調査も対応可能です」といった、具体例を交えた提案をいただけると、とても助かります。
特に、特許は素人にはハードルが高く、意匠や商標と比べても難しさを感じています。そうした中で他社特許の見方や検索のコツ、コア特許の番号など、ちょっとした情報をもらえるだけでも大幅な時間節約につながり、本業に集中しやすい環境が生まれます。
こうした支援により、当社の知財活用は一気に進んでいくことでしょう。弁理士の方々が持つ俯瞰的な視点と専門的な分析力は、当社にとって単なる法務的サポートではなく、事業の成長エンジンそのものであり、連携が強化されることで、私たちは技術開発と市場展開の両面で、より大胆かつ精度の高い挑戦が可能になっていくものと信じています。