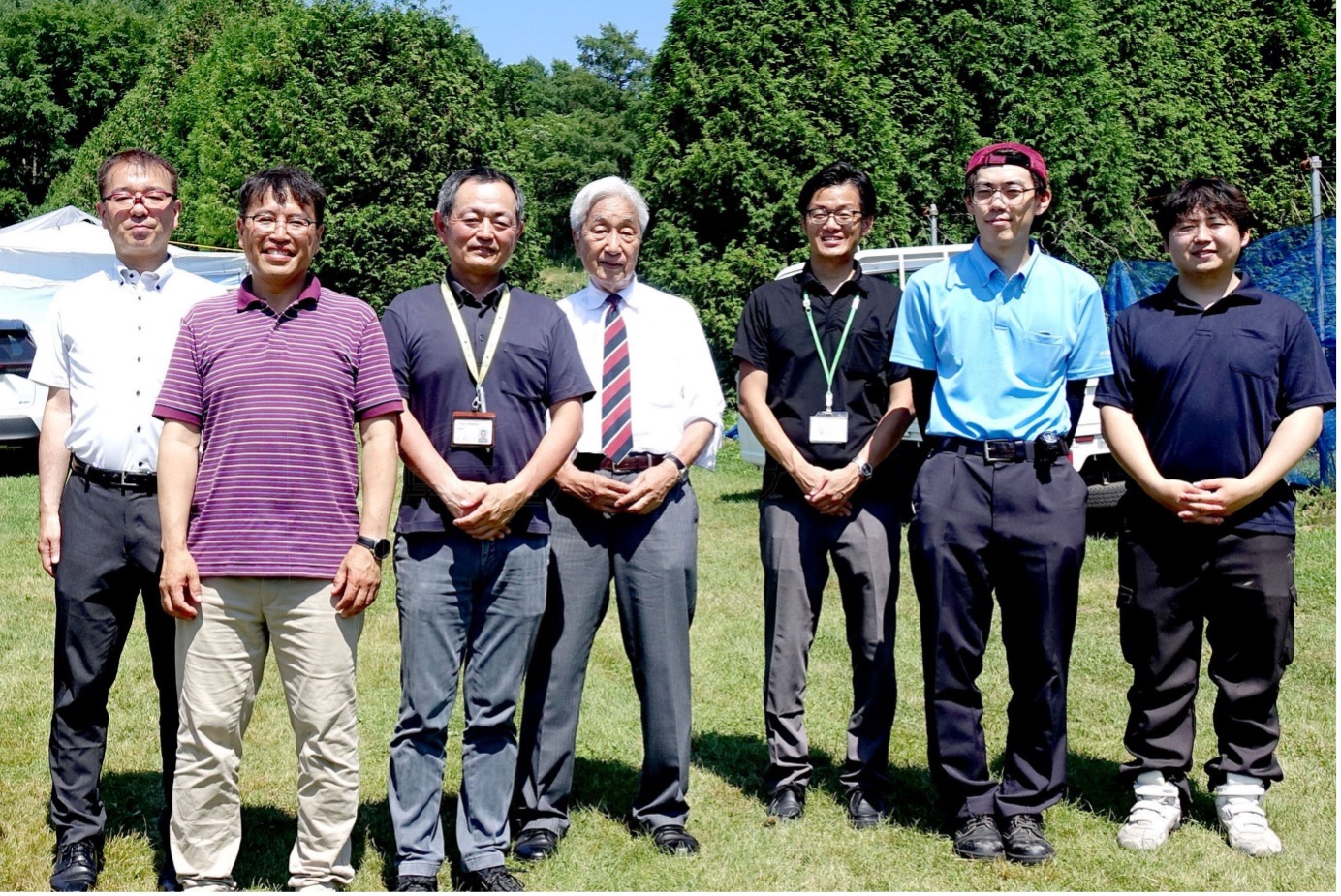事例紹介
厚真産ハスカップ
「 厚真 産ハスカップ」は、北海道厚真町特産の果実「ハスカップ」のブランド名で、地域団体商標登録もされています。地域団体商標は、地域ブランドを保護することで地域経済の活性化を目指すため2006年に導入された制度。厚真町はハスカップの作付面積日本一を誇り、地域団体商標登録を武器に厚真産ハスカップのブランド化を推し進めています。
この記事では、知的財産の活用事例の一つとして地域団体商標を活用した地域のブランディングに注目。厚真産ハスカップとは何か、なぜ地域団体商標登録を目指したのか、地域団体商標をどのように生かしていくのかを探ります。
今回お話を伺ったのは、「厚真産ハスカップブランド化推進協議会」を構成する以下の組織の方々です。
- 厚真町役場 産業経済課 経済グループ 主査 澤井順英さん
- 一般社団法人 厚真町観光協会 事務局長 原祐二さん
- 株式会社あつまみらい 代表取締役 兼 厚真産ハスカップブランド化推進協議会 会長 山口善紀さん
- とまこまい広域農業協同組合 農産部 農産課 係長 森昌弘さん
- とまこまい広域農業協同組合 農産部 そ菜園芸課 伊藤賢治さん

厚真産ハスカップとは何か。そもそもハスカップはどのような果実なのか
ーーそもそもハスカップとはどのような果実かということから教えてください。
森さん
「ハスカップは、北海道や本州の標高1500mなどの高山帯と、シベリアなどに自生している落葉低木です。国内では、厚真町や苫小牧市などを含む 勇払 原野が日本最大の群生地です。厚真産ハスカップは例年6月下旬から7月中旬にかけて、酸味の強い青紫色の小さな実をつけます。ハスカップは機能性に優れた果実で、ビタミンCはレモンの1.8倍、ポリフェノールがブルーベリーの5倍以上含まれ、抗酸化作用や抗糖化作用があると言われています」

ーーもともとは野生の果実ということなのですね。
山口さん
「昔は苫小牧市民や近隣の人たちが勇払原野に自生しているハスカップを取って食べたり、苫小牧市のお菓子メーカーが市民から買い付けたハスカップの実を使ってお菓子を製造したりしていました。そのため、苫小牧市民などこの地域の方々は、実がなる時期に生のハスカップを食べる習慣があります」
ーーなぜ野生の果実を厚真町で栽培をするようになったのでしょうか。
山口さん
「1980年代に勇払原野で大規模な工業開発が行われるようになって、ハスカップの木が無くなるかもしれないという危機感が広まりました。そこで、厚真町の農家などが勇払原野に自生していたハスカップを町内に移植を進めたので、厚真町ではハスカップ栽培が盛んになったのです。私自身がハスカップ農家なのですが、母が移植をして私の家ではハスカップ栽培を始めました」
森さん
「今ではハスカップの作付面積は日本一で、主に苫小牧市民向けの生食のほかに、菓子などの原材料として幅広く商品化されています。また、町内のハスカップ農園ではハスカップ狩りも楽しめるところが何軒もあります」
ーー厚真産ハスカップの定義や規定などはあるのでしょうか。
山口さん
「厚真産ハスカップは、厚真町で生産されるハスカップの総称です。もともと野生の木ということもあり品種はさまざまで、木ごとにハスカップの大きさも味わいも異なります。私が栽培し始めたときは5,000種類くらいあったハスカップの木から良質なものを30本くらい選抜しました。さらに甘みが強いなど味のよい木を選抜して挿し木(植物の一部を切り取って新しい苗を育てる方法)をし、育てるようにしてきました。その結果、苦味があまりなく糖度の高いハスカップを増やすことができました。これらは甘みの強い「ゆうしげ」や酸味と甘さのバランスがよい「あつまみらい」という、厚真町限定の品種として栽培されています。厚真町限定のこの2品種はもちろん、在来の野生種も厚真町内で栽培されたものが厚真産ハスカップです」
地域団体商標「厚真産ハスカップ」取得の経緯と目的について
ーー厚真町で栽培されるハスカップを地域団体商標登録しようと動き出したのはいつ頃でしょうか。
森さん
「2016年2月です。2015年の6月に町内の生産者や事業者とJAとまこまい広域、厚真町役場、商工会や商工会員などの関係者や有識者が、町役場を事務局にした『厚真産ハスカップブランド化推進協議会』という組織を設立しました。厚真産ハスカップの知名度のアップや販売促進をしていくためです。この組織ができて動き出してすぐに地域団体商標を取ろうという話になりました」
ーー地域団体商標登録を目指した理由やきっかけなどは何でしょうか。
山口さん
「明確な理由は定かではないのですが、町の予算を使っている以上、まずは実績を作ろうという考えからだったと思います。少なくとも、厚真産ハスカップを盛り上げていくためという点は変わらないです」

ーー地域団体商標登録されたのは2024年ということですので、登録までかなり時間がかかったということなのですね。
伊藤さん
「そうですね。実は以前、JAとまこまい広域で『ほべつメロン』というむかわ町穂別地区のブランドメロンを地域団体商標に申請をして、比較的すんなり登録されたことがありました。その実績があったので比較的すぐ取れると思っていたのですが、なかなか進まず時間がかかってしまいました」
澤井さん
「年度が経つと部署移動で担当者が変わるんですよね。そうすると担当者がまた一から理解して覚えていくことになるので、組織間の連携がなかなかうまくいかなかったということもありました。2023年度に北海道経済産業局の地域ブランド確立促進支援事業というものがあって、こちらの支援事業を通じて弁理士さんをつないでいただきました。その結果、2024年10月22日付で地域団体商標登録されたという経緯です」
地域団体商標を取得したことによる変化と課題
ーー地域団体商標登録されてから半年少々なのでまだ見えにくいかもしれませんが、登録をきっかけに変化したことはありましたか?
伊藤さん
「生食用として出荷している苫小牧市場の今年の初セリが史上最高値でした。地域団体商標登録されて価値が認められたのだと思います」
森さん
「あと、引き合いが明らかに増えました。今までは、加工用のハスカップは製造メーカーが買い取り、生食用のハスカップは主に苫小牧市民向けなので苫小牧の市場がセリで買い付けてくれるという流れで長年続いてきました。地域団体商標登録されてからテレビなどメディアで取り上げられたこともあって、札幌の市場などから『取引したい』『いくらでも買う』など問い合わせが来るようになりました。登録されたことによる大きな変化だと思います」
ーー地域団体商標登録されたことによるブランディングの成果かもしれませんね。単価アップや販路拡大のほかに利活用していることはありますか?
原さん
「登録される前から取り組んできていたのですが、観光客向けのハスカップ収穫体験もあります。今まで訪れる方々は苫小牧市民など近隣の方々が中心でしたが、厚真産ハスカップの知名度が上がるにつれ、札幌の方や北海道外の方々が増えました。登録されたことでさらに観光客の来客が見込まれます。ただ、収穫体験のやり方については過渡期で見直しをしています」

ーー収穫体験の見直しとはどのようなことでしょうか。
原さん
「苫小牧市民などの方々が農家さんを訪れていた目的は、収穫の体験をすることではなく、生のハスカップをスーパーなどではなく農家さんから直接買うためです。安く買えるので。そのため、いくつか味見をして気に入れば5キロとか8キロとか買っていきます。ただ、遠方から訪れる方々は生のハスカップを買うためではなく、収穫の体験を楽しむために訪れます。収穫をしてその場で食べることが第一の目的なので、お土産としては買っていかないことが多いです。農家さんの直売を前提にした一般客の受け入れ体制から、観光客の体験を前提にした一般客の受け入れ体制にシフトしていく途上です」
山口さん
「味見をして買ってもらうことが前提だったので、以前はどの農家さんも入園料を取っていなかったんです。そこへ収穫を楽しむことが目的の方が来ると、とにかく取りまくって食べまくって何も買わずに帰る方とか、買っても数百gとか少量とかなんですよね。いちご狩りとかさくらんぼ狩りと同じような感覚でいらっしゃいます。ただ無料で食べさせるだけで農家さんにはほとんど何も残らないとなると、さすがにやっていけないですよね」
ーー無料で収穫して食べられて購入もしてもらえないとなると、商売としては成り立たないですよね。
山口さん
「そうなんですよ。なので、私のところは数年前から入園料をいただくようにしました。有料化したら来園者がガクッと減りましたが、致し方ないことです。厚真産ハスカップが登録されて、より認知度や人気が高まっていくこの先の未来を考えると必要なことだと思っています」
原さん
「今は山口さんのほかにも、いくつかの農家さんで入園料をいただいています。例えば、買う方も買わない方も入園料を500円いただくとか、1,000円いただいてkg単位で買って帰る方は入園料をお返ししますとかというパターンもあります。ただ、農家さんごとに置かれている状況が違うので、みなさんが入園料をいただくパターンを導入しているわけではないです」
山口さん
「入園料をいただくということは、受付など入園料をいただくための人手も必要になります。農家さんによっては『ただでさえ収穫で忙しいときにそこまで人手を割けない』『人を雇うほどの売り上げが見込めるわけでもない』ということで踏み込めないところも多いです」
原さん
「今は、買うための味見の体験提供から、収穫を楽しむための体験提供へとシフトしていく過渡期なのだと思います。一般向けの小売りや収穫体験をしている農家さんに対しては、『入園料をいただくようにしませんか』という話はしています。観光客向けには厚真産ハスカップの収穫体験ができる農家さんのマップも作っていて、入園料をいただく観光農園を後押ししていくようにもしています」
地域団体商標「厚真産ハスカップ」の未来
ーー単価が上がり、さらに販路も増える見通しで、観光目的の来客も期待できるということですと、収量アップや栽培面積の拡大など増産が求められている状況でしょうか。
山口さん
「増やしたいけど、なかなか増やせないというのが実情です。ハスカップの収穫は基本的に機械での作業ではなく一粒ずつ手摘みしているんです。慣れていない方がハスカップを摘むと実が潰れたり汁が出てきたりするので、スーパーに並ぶような商品価値にはなりにくいです。熟練の方が摘むと実から汁が出ることはあまりなく、商品として出荷できるものになります。仮にいくら栽培面積を増やしても、手摘みの経験が豊富な方のマンパワーが必要なので、収穫量には限界があります」

ーーハスカップは機械での収穫が難しいのですね。
山口さん
「海外では機械で収穫している地域もあるようです。ただ、機械で収穫したものは加工用になるんですよ、潰れたり汁が出たりするので。厚真産ハスカップは加工用として出荷しているものもありますが、歴史的経緯から主に苫小牧市民などに向けた生食用なので、手摘みでの収穫が必要です。もし仮に厚真産ハスカップを機械収穫するのであれば増産することはできると思いますが、生食用ではなく加工用にシフトしていく必要があります。ただ、加工用は市場でのセリではなくメーカー買い取りなので、なかなか単価を上げにくいという課題もあります」
ーー手摘みが基本となると、熟練した農家さんが増えていく必要がありそうですね。
山口さん
「そうなのですが、協議会を立ち上げた2015年頃と比べると農家さんの数が減っているのが実情です。当初町内に100軒くらいハスカップ農家がありましたが、現在精力的に生産している農家は60軒くらいです」
ーー農家さんが減ってきている理由は何でしょうか。今後ブランディングが進んで需要が高まる中で供給を増やすには、生産者を増やしていくことが必要に思われます。
山口さん
「いくつか理由があるのですが、一つは農家の高齢化が進んでいることと、2018年に発生した北海道胆振東部地震の影響です。歳を重ねると収穫作業が若い頃のようにスムーズに進まないので収量は下がってしまいますし、後継者がいなくて栽培をやめてしまう農家さんもいます。それと、厚真町で震度7の大地震が起きて農家さんが2軒亡くなられてしまいましたし、栽培地も地震で崩れるなどして大幅に減りました。厚真産ハスカップの生産量も2018年は18トンありましたが、2024年は高温の日が続いたこともあり収穫量が落ちてしまい4トンでした。現在、厚真産ハスカップの生産力の限界は10トン前後かなと思われます」
ーー生産者の増加や収量のアップに関して、現実的にはなかなか厳しい状況かと思われますが、何か手立てや支援などはあるのでしょうか。
澤井さん
「役場では別の部署では10年くらい前から厚真産ハスカップの栽培促進のために苗木の補助を行ってきました。人手という面では、地域おこし協力隊を活用しています。例えば、ハスカップのお酢を作っていた方が地域おこし協力隊として入って、厚真産ハスカップの酢を製造して販売するための起業準備をしています」
山口さん
「その方のほかにも、ハスカップ栽培で独立するために地域おこし協力隊でやってきたという方もいます。農家さんは高齢化が進んでいて後継ぎがいないところも多いので、第三者継承(経営や事業を親族や従業員以外の第三者に引き継ぐこと)を前提に活躍しています」
ーー担い手が少しずつでも増えていくと、将来的には生産量のアップにも期待が持てますね。
澤井さん
「そうですね。町としては、厚真産ハスカップの認知向上とともに、さまざまな農家さんや産業の振興を後押ししていきたいと思います。厚真産ハスカップに関しては協議会ができてから取り組んできていることではありますが、今回登録されたことをきっかけにより進めていきやすくなったと思います」
ーー地域団体商標に登録されることが目的ではなく、ブランディングの武器やツールの一つであり、厚真産ハスカップの認知向上と地域経済の活性化や雇用の創出などを目的とされていることがよく分かりました。厚真産ハスカップのブランド価値のさらなる向上と町の発展が進み、今まで取り組まれてきたことが実を結ぶことを期待しています。本日はどうもありがとうございました。